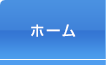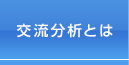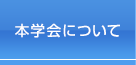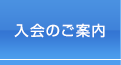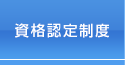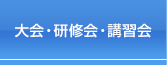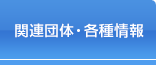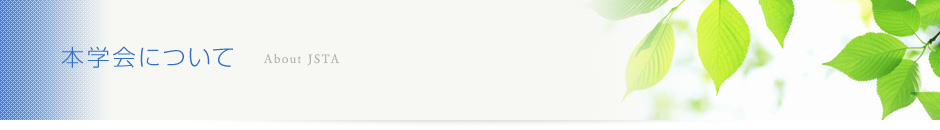桂学術奨励賞
桂学術奨励賞は、交流分析に関する優秀な論文に対して贈られる賞です。
桂学術奨励賞選考委員会によって推薦され理事会の承認の後、会員総会で表彰されます。
桂学術奨励賞選考委員会によって推薦され理事会の承認の後、会員総会で表彰されます。
受賞者一覧
第30回(2023年度)
該当者なし
第29回(2022年度)
該当者なし
第28回(2021年度)
小泉光世(北海道大学大学院理学院)
心理ゲーム多発学級における授業中のコミュ二ケーション改善に関する実践研究
第27回(2020年度)
中西美和(大阪女学院大学)
やりとりを行う2者の関係性からみたラケット感情の経験プロセスの検討
第26回(2019年度)
平出麻衣子・宮本せら紀(東京大学大学院医学系研究科)
新版 TEG3(紙版およびコンピュータ適応型テスト版)の開発
第25回(2018年度)
該当者なし
第24回(2017年度)
該当者なし
第23回(2016年度)
徳丸史郎(法政大学大学院政策創造研究科)
精神障害者の自我状態とソーシャルスキルに関する研究
第22回(2015年度)
白井幸子(ルーテル学院大学)
治療者は何によって傷つき、何によって癒されるか
第21回(2014年度)
西川和夫(財団法人田中教育研究所)
自己志向他者志向エゴグラムIUE下位尺度の自己志向『順応した子ども』IACと他者志向『順応した子ども』UACの心理機能比較
第20回(2013年度)
該当者なし
第19回(2012年度)
木下香織(新見公立大学)
認知症高齢者のエゴグラム尺度の作成と妥当性・信頼性の検討
第18回(2011年度)
島田凉子(人間総合科学大学)
抑うつとパーソナリティーの関係についての研究
-交流分析の視点から-
-交流分析の視点から-
第17回(2010年度)
押川聖子(神奈川大学)
ドライバーズの心理的・行動的諸側面の検討
第16回(2009年度)
高品孝之(北海道大学大学院教育学院)
禁止令「存在してはいけない」の分類と境界例心性における感情易変対応の一事例
第15回(2008年度)
橋元慶男(岐阜聖徳学園大学教育学部)
自我機能とユーモアとの関係
-IUエゴグラムを用いて-
-IUエゴグラムを用いて-
第14回(2007年度)
齋籐瞳(同志社大学大学院文学研究科)
自我状態のシフトと基本的構えの関連についての検討
-認知システムと反応システムの観点から-
-認知システムと反応システムの観点から-
第13回(2006年度)
中西美和(同志社大学大学院文学研究科)
ラケット感情とエゴグラムパターンとの関連
杉山雅美(駒澤大学大学院人文科学研究科)
自我状態の透過性調整力に関する研究(2)
-その促進技法、及び自己認知との関連による検討-
-その促進技法、及び自己認知との関連による検討-
第12回(2005年度)
辻裕美子(国立精神神経センター国府台病院)
再決断療法を取り入れたがん患者への心理療法の研究
第11回(2004年度)
村上正人(日本大学板橋病院心療内科)
サイコオンコロジーと交流分析 -現代人の死生観と「時間の構造化」-
第10回(2003年度)
篠崎麻由子(早稲田大学大学院 文学研究科)
青年の成年のドライバーズと自己評価が成長意欲に及ぼす影響
-共分散構造分析による一研究-
-共分散構造分析による一研究-
第9回(2002年度)
芦原睦(中部労災病院・心療内科部長・愛知県)
ストレス対処行動における交流分析的検討(第1報)
ストレス対処行動と自我機能仮説
(交流分析研究・第27卷2号)
森山裕美(中部労災病院・心療内科心理士・愛知県)
ストレス対処行動と自我機能仮説
(交流分析研究・第27卷2号)
ストレス対処行動における交流分析的検討(第2報)
Coping Behavior Egogram(CB-E)作成の試み
(交流分析研究・第27卷2号)
Coping Behavior Egogram(CB-E)作成の試み
(交流分析研究・第27卷2号)
第8回(2001年度)
太湯好子(川崎医療福祉大学)
機能的自我状態モデルにおけるPermeability Control Powerと看護適性とメンタルヘルスとの関連(交流分析研究・第26卷2号)
第7回(2000年度)
小澤真(大分県立芸術文化短期大学)
生徒理解のための交流分析の活用 ~高校生の学校ストレス認知とエゴグラム~
(交流分析研究・第25卷2号)
(交流分析研究・第25卷2号)
第6回(1999年度)
中原理佳(東京大学医学部附属病院分院心療内科)
摂食障害における自我状態、基本的構え
(交流分析研究・第24卷2号)
塚田縫子(岩手大学看護学部)
(交流分析研究・第24卷2号)
食行動調査(EAT)とエゴグラム(TEG第2版)による摂食障害の検討
(交流分析研究・第25卷1号)
(交流分析研究・第25卷1号)
第5回(1998年度)
高橋類子(新潟大学教育人間科学部)
生活科学教育における「生き方を見直す」授業実践と評価
第4回(1997年度)
中村芙美子(プール学院大学短期大学)
吃音に苦しむ女性オフィスワーカーに対するコミュニケーション改善の試み
-TA的アプローチによる言語指導と心理療法の併用-
-TA的アプローチによる言語指導と心理療法の併用-
第3回(1996年度)
該当者なし
第2回(1995年度)
福間笙子(関西カウンセリングセンター)
対人不安を訴える青年期女性との面接過程 -ゲームの解消と禁止令解除をめざして-
第1回(1994年度)
西川和夫(三重大学)
自己志向・他者志向エゴグラム作成への可能性